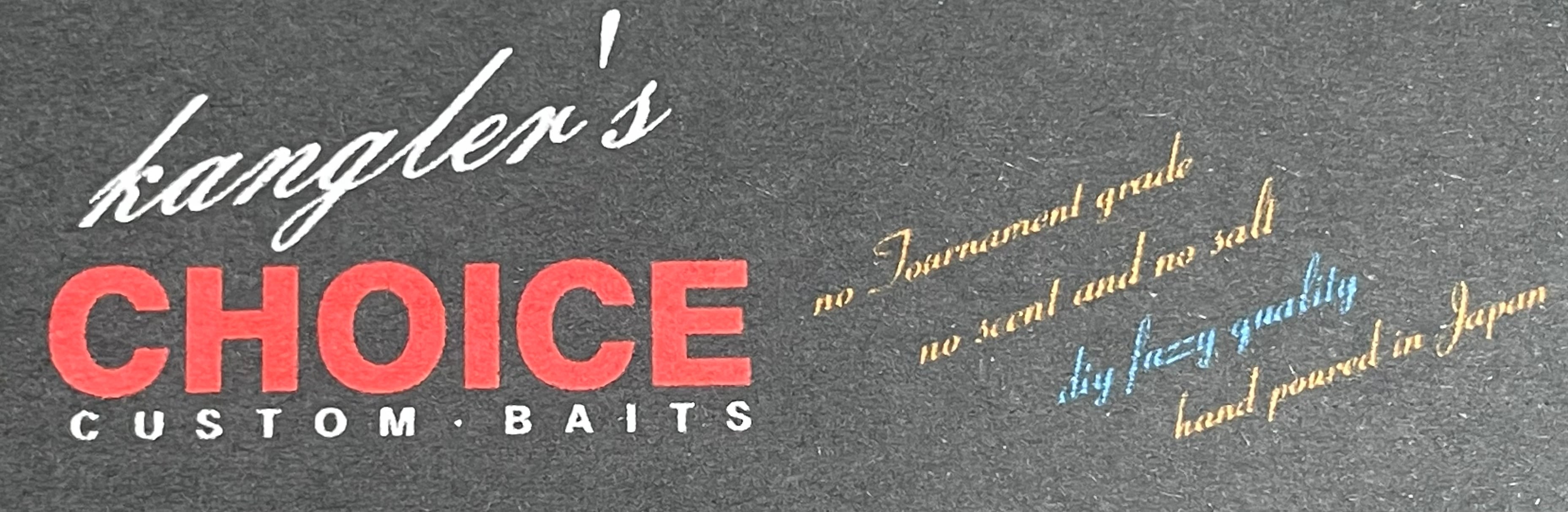ぼんやりとした開発経緯は一昨年だろうか?コロナが始まる前後の夏だった気がする。
うちのシャッドテールは釣れると自負しているけど、当時ずーっと言われて引っ掛かっていた言葉
【高活性時に弱い】
製作者としては【そういう隙間的なルアーなんです】としか言いようがなく、
使いどころが限定的で商品説明をすることがないうちではかなりマイナスのイメージであることは認識していたけど。
そんな中、何でか忘れたけどバスやんとお茶をした。こいつは琵琶湖の釣りに関しては忖度をしない。
それって大人の付き合いとしてどうなんか?とおもう。
ある意味『レジャーフィッシング』の俺と『雪の降る中、水につかる危ないやつら』とはやはり感覚がずれていた。
多分、関東のそれとはちょっと異常性が違う。
うちのは渡してあるので感想はまぁ釣れるけど、というから何で使わないの?って聞いたら
じゃあ今の俺の一軍ルアーよりもデカいのを引っ張れるんですか?
と言われた。
あぁそうかタフとかプレッシャー云々は別として何か琵琶湖ならではの目標があってそれをクリアするためにかなりストイックなんだなーと。
じゃあ新型を作るならどんなもんが良いのかって聞いたら、
『針持がよくて4面使えるやつが欲しい』という。
当時はデータの作り方は今よりもわからず、何が何だかわからず取り組み始めた。
でもむかつくから絶対納得するマルチロールモデル作ってやる
と思った。
そうとなるとどんなもんが良いか?尖ったスペシャリティモデルが良いだろうけど俺がそれは嫌。
目先で形だけ真似てもダメだ。
でも絶対的なパワーのあるモデル…そして今はやっていない廃れたモデル…
そうだ。パドルとビッグカーリーとシチュエーションで使い分けられるであろうと復活させようとしていモデルがあるじゃないか…
バレーヒルのレイクフォースシリーズ【Gワグラー6” 】
※一番左が積層式、透明が光造形。一番右のピンテールは積層式には厳しいみたい。高額機器ならわからんけど。
本当はGワグラーの頭部形状にしたかったけどそれすらできなかった頃。ほぼA氏ファミリーの手が入っているw
(そして上のボディ出力では欠陥が見つかりVer2に設計を大きく変更していくことになった。
1stに関してはレギュラーラインナップにはあまりにもマニアックすぎるので新型ができたら使用書アナウンスしておまけにでもつけようかと。本当にそのままだと動かないので。だがそれが良い。そしてこの発想がVer2へと発展する。)
これならボディ共通でテール変化でバリエーション出来る!!
扁平なので使い分けもできるじゃないか!!俺天才!!とか思った。
とりあえずデータの作り方をA氏ファミリーに聞いてたり作ってもらったりバスやんに出力してもらったけど、A氏の光造形のモデルをバスやんのサイトでみて厚かましくもお願いしたら快く出力してくださり、A氏ファミリーにおんぶにだっこのデータ製作が始まった。
が…
シャッドテールだとパワーは出しやすいし説明しなくてもいい。が4面使えない…
十字にする、双葉の様にする…
出来なくもないけど、それって4面使うためだけのデザインで魚を引っ張るデザインじゃないよね?
いや、うまくいけばそれもありだけど、いったいどれだけデータどりしなくてはいけないのか?
しばらく堂々巡りが続いた。
ああ、あれならいけるだろう。
たどり着いたのは球体のボールテール。
だがしかし、俺はネクストワンの時もオゴキューも20年以上の時を隔ててリバイバルされたモリックスの時もやはり釣れなかった。
好きで好きで愛してやまなく使い続けても釣れなかったドラゴンエッグぐらい相性が悪い。
それを今、身銭をどれだけ切るかわからない沼につぎ込めと…
しかもまだオゴキューは現行品(開発当時)として出てるじゃねーか…
でももうやり始めちゃったからしょうがない。
オゴキューを見ると動き出しの水嚙みが悪いからきっかけを作っている。
ふむ。球なら水逃がすもんね。じゃあ平面作ればいい。じゃあ4面体?
アンキロサウルスっぽくていいしテールにラバーさして流行りのあれっぽく…でも気泡をどうするよ?
ならいっそのこともっと多面体にすればどこかしら平面に水受けるしと。
しかしデータ製作が今でも難しい。泣いていたらパパっとデータを神が授けてくれた。
ここにきて意識が固まってきた。
冬のデカバスをメインターゲットにした上でオールシーズン使えるマルチベイト。
ここで【動かしたい人】と【動くことを嫌う人】に分かれる。
儲けたいのでこの両方を取り込みたい。
主題は『動かないものから動くものへ』
みための派手なボールテールですがただ巻きでは意外と動きません。
時々千鳥るクランクの様にあいまいな動きです。ピッチも早くありません。
比重自体は硬度によりますが1前後なのでデッドスローでも沈下速度は早くありません。フックレスなら浮きます。
ここを基準にして設けたリブを少しずつカットしたり切れ目を入れることによってただ巻きやリッピング、ジャークやシェイクに微細な味付けを加えていく感じです。
市販品と比べるとどうしても割高になってしまうので、ボールがとれてもピンテールとして。
リブがボロボロになったらイモグラブとして。しゃぶりつくせるような設計をしています。
少し前から気になっていたマテリアルの癖がなんか確信に変わったので追い込めたテール寸法ですね。
扱い始めて4-5年は立つでしょうか?例えばソフト、ミディアム、ハードのデフォルト硬度ラインナップに添加剤を入れてハードをミディアムくらい柔らかくする、ミディアムをソフトくらい柔らかくした場合とデフォルトのミディアムやソフトより何故かもっちりする。
A剤とB剤の配合で硬度は決まっているので後からA剤だろうがB剤だろうが入れたところで何故変質したように思うのかが不思議。
もしかしたら気のせいかもしれないけどなんかやっぱり違う。
イメージで言えばデフォルトはゼリーの様にフルフルだけど切れ目が入ると一気に切れてしまうかんじで、
添加した場合はわらび餅の様にもっちりと粘りが出てる気がする。
↓Ver2のテールレスリブ全カット動画。ボディ後半はΦ3mmくらいの芯が通っている。
これでフルキャストしてもスキップしても別に何か起こらない。(この時は玉は成形不良で流れ切れていない。)
上の画像の真ん中の緑はVer3、赤はVer3改。
どちらの方向で行くかわかりませんが、Ver3の方が個人的には良い感じ。
どちらにしても設計ミスと新しく検証できたことがあるのでそれを盛り込んだVer4までテストしないとです。
そして嫌がらせの様に厳冬期が短い…
明日は結果が出ている3.5インチのお話。